少し前になりますが、国立新美術館にてリビングモダニティ住まいの実験、という展示に行ってきました。1920年代から70年代、ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエ、アルヴァ・アアルトらが「こんな暮らしってどう?」と大胆に提案した実験的住宅が並ぶ――それがこの展覧会。世界各地から選ばれた約14の名作住宅を通じて、いかに「住まい」が刷新されてきたかが体感できます。写真・図面・スケッチ・模型・家具・テキスタイル・食器・雑誌・映像と盛りだくさんの展示内容でした。
展示は、以下の7つの視点から住宅を解剖する形で構成されていました
- 衛生:お風呂や洗面の動線を居室とつなげて清潔を設計
- 素材:鉄やガラス、新素材を大胆に用いた実験
- 窓:水平連続窓で光と風を取り入れる新しい居空間
- キッチン:調理・収納・動線を総合的に再構築
- 調度:家具まで住まいの一部としてデザイン
- メディア:書籍や住宅展示、雑誌で住まいのイメージを拡散
- ランドスケープ:自然との一体感を取り込む設計アプローチ
私がここに住みたいなーと思ったのはル・コルビジェ設計のヴィラ・ル・ラク(スイス・1923年)でした。横長の建物に目の前の湖の景色を家に取り込むような大きな横長の窓。そして家の中を回遊できるような間取りで解放的にしています。小さな家ではあるのですが住みやすそうでした。この家の特徴は大きな水平連続窓を取り入れたことでしょう。(ヴィラルラクの写真は撮り忘れました・・)
もう1点、楽しそう!と思った建築は菊竹清訓、菊竹紀枝のスカイハウス(日本1958年)でしょうか。日本の経済が発展していたころ、建築も生き物のように成長したり変化したりする必要があるというメタボリズムという考えが今れ、家族の変化に合わせて姿をかえてきた家です。地面から浮かぶように作られていて、部屋をつけたり外したりできるようなムーブネットという仕組みになっていました。そして上階がやはり開放的な回遊の間取りで住みやすそう、と感じました。

それから、今はリサイクルの家?工場に余っていた部品でつくった家、ジャンプルーヴェのナンシーの家(フランス1954年)なんかはSDGSが謳われる昨今、その思考を見直してみる価値のある建築だと感じました。山の傾斜にたたずむ姿もなんだか自然との融合を感じて惹かれました。
日常の「住まい」は実は、100年前から建築家たちが緻密に設計と実験を重ねてきた成果。その歴史やアイデアを、実物模型や家具、資料から心地よく感じられました。

今回の企画展はここ最近では一番テンションがあがってしまい何時間でも見ていられるほどでした。「機能って美しい」「暮らしに遊び心を」そんなモダニズムの精神を、自分の生活にも取り入れてみたくなる。住宅って面白いな、と素直にワクワクした企画展でした。
ブログランキングに参加しています✨
1日1回クリックしていただけると励みになります。
よろしくお願いします✨

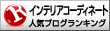











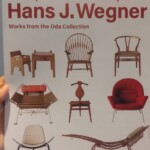

この記事へのコメントはありません。